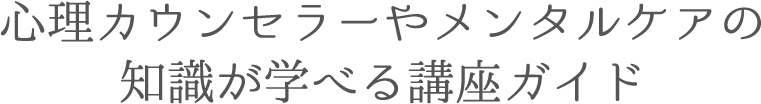「心理カウンセラーになりたい」、「メンタルケアを学びたい」あなたを応援するサイト
メンタルケア関連の資格

メンタルケアの資格を取得するメリットと、民間の機関・団体が認定している主な資格について解説しています。メンタルケア心理士・ケアストレスカウンセラーなどの仕事内容と、資格取得の方法についても必見です。
メンタルケアの資格を取得するメリットとは
メンタルケアとは、人が抱える悩み・ストレスを解決するためのサポートを行うもの。「メンタルケア心理士」「メンタルケアカウンセラー」などの資格がありますが、どれも民間資格となっています。
メンタルケアの資格を持った専門家は、教育・医療・介護・一般企業などでの活躍が見込めるほか、自分自身の生活や仕事を充実させるために知識を活用することもできます。
そのため、資格取得だけでなく、さまざまな理由でメンタルケアを学ぶ人が多いのです。
- 医療・福祉・介護などの仕事に活かしたい
- ボランティア活動に役立てたい
- 人とのコミュニケーションを良好にしたい
- 会社の部下のメンタルケアに活用したい
- 教員として生徒の気持ちを深く理解したい
- ひとつの知識としてメンタルケアを学びたい
メンタルケアを学べるスクール・通信講座は数多くありますが、大切なのはその内容。これまでの受講生数(実績)や体験学習の多さ、テキストの分かりやすさ、サポートは充実しているかなどをチェックし、自分に合ったスクールを選ぶようにしましょう。
メンタルケアの主な資格
メンタルケア関連の資格は似たような名前の資格が多いものの、資格の取得によって得られる知識やスキルは大きく違います。
今回は、
- メンタルケア心理士
- ケアストレスカウンセラー
- メンタルケアカウンセラー
という3種類のメンタルケア資格について解説します。
メンタルケア心理士
メンタルケア心理士とは、メンタルケア学術学会と一般財団法人・生涯学習開発財団、一般財団法人・ヘルスケア産業推進財団の3団体が認定を行っているメンタルケアの民間資格です。
「メンタルケアカウンセラー」の上位版ともいうべきもので、さらに上位の資格として、「メンタルケア心理専門士」という資格もあります。
メンタルケア心理士資格に合格すると、医療・福祉・教育・産業・公共サービス等において、相手からの相談を受けたり心理カウンセリングを行ったりする上で最低限必要とされる基礎力があることを証明できるのです。
ちなみに、2018年度からは文部科学省の後援を受けた「こころ検定」に試験そのものが統合されており、「こころ検定2級」に合格すれば、「メンタルケア心理士」として登録できるようになりました。
メンタルケア心理士を活かせる仕事

メンタルケア学術学会によると、メンタルケア心理士の受験者でもっとも多いのは30代。さらに、受験者の23%は医療福祉関係者であり、20%は会社員となっています。[注1]
資格を単独で仕事につなげるというよりは、さらに上位の資格へとつなげるためのステップアップとして取得する方が多いようです。ただし、企業の人事担当や役所の福祉課など、培った知識が直接役立つ仕事も少なくありません。
メンタルケア心理士の受験資格
こころ検定2級試験は、受験料さえ払えば誰でも受けられます。もともとは、メンタルケア心理士試験が心理学関係の一定の講座を修了していたり、認定心理等の資格を持っていたりする人だけが受けられる試験だったので、受験資格は大幅に緩和されている状態です。
メンタルケア心理士の試験内容
こころ検定2級試験の出題範囲は、
- 精神解剖生理学について
- 精神医科学について
- カウンセリングの基本技法について
となります。人間の心を科学的に分析していく上で、必須となる知識を幅広く問われることになるでしょう。なお、メンタルケア心理試験は在宅受験方式だったのですが、こころ検定についてはCBT方式を採用しています。最寄りの試験会場に足を運び、コンピューターを使ってランダムに出題される選択式の問題を解いていくというやり方です。
メンタルケア心理士の合格率と難易度
メンタルケア学術学会の資料によると、平成29年の平均合格率は54.2%。[注1]
試験の名称が変わり、文章問題がなくなったとはいえ、試験の難易度は高いです。ただ、受験資格が優しいため、独学とスクールを組み合わせれば十分合格できるでしょう。
[注1]メンタルケア学術学会:メンタルケア心理士(R)認定試験について
その他の資格と違う点
メンタルケア心理士は、カウンセリング技術の上手さを証明するのではなく、カウンセリングの歴史や基礎知識の獲得を目的とした試験です。心理学に関する研究をしたい、心理学の基礎知識を学びたい、心理学を学ぶ人たちと学会発表等を通じて交流したいという人に向いています。
ケアストレスカウンセラー
ケアストレスカウンセラーは、一般財団法人・職業技能振興会が認定しているメンタルケアの民間資格です。ストレスを抱えている人に対して、心理学やカウンセリングの専門知識を使った的確なアドバイスができるようになるのが目的とされています。
カウンセラーやアドバイザーとして、実際に活動していくための知識を問われるのが特徴です。
ちなみに、ケアストレスカウンセラーはもっとも基本的な心の問題やカウンセリングについて学べる基礎資格であり、
- 企業中間管理職ケアストレスカウンセラー
- 高齢者ケアストレスカウンセラー
- 青少年ケアストレスカウンセラー
といった、よりターゲットを絞った専門資格も用意されています。
ケアストレスカウンセラーを活かせる仕事

基礎資格であるケアストレスカウンセラーを取得すると、身近な家族や友人、知人といった他者の相談はもちろん、自分自身が感じているストレスにも対処可能です。
一方、企業中間管理職ケアストレスカウンセラーを取得すれば、管理職として部下や上司のメンタルケアも可能になります。とくに、部下のマネジメント能力は昇進にも関わってくるため、スキルアップのために取得を目指すのがおすすめです。
介護や福祉業界で働いている人は、高齢者ケアストレスカウンセラーを活かすことができます。介護疲れに悩む家族や、高齢者本人のストレスにうまく対処できるようになれば、自身が受けるストレスも軽減できるでしょう。
青少年ケアストレスカウンセラーに関しては、子育て中のご両親や学校、塾といった教育現場で働く人に役立つ資格です。
どれも合格すればすぐに独り立ちできるという種類の資格ではありませんが、合格後は実技を伴うフォローアップ研修を受けることができるため、カウンセリング技術も磨けます。
ケアストレスカウンセラーの受験資格
ケアストレスカウンセラーの受験資格は、18才以上であることのみ。
ケアストレスカウンセラーの試験内容
試験問題は、一般常識問題に加えて、公式テキストからの出題です。試験方法はCBT形式で、全国220ヶ所以上の会場で受験可能。合否は試験終了直後にわかるため、気軽に受験できます。
ケアストレスカウンセラーの合格率と難易度
一般財団法人・職業技能振興会の資料によると、問題の正答率が70%以上であれば合格です。[注2]
公式テキストがあるため独学でも合格は可能ですが、勉強していなければ受からないでしょう。
[注2]一般財団法人 職業技能振興会:ケアストレスカウンセラー
その他の資格と違う点
受験資格が非常にゆるく、合格後のフォローアップ研修でカウンセリング技術を学べるのが最大のポイントです。実生活や仕事に役立つメンタルケアのスキルを求めている方は、受験を考えてみましょう。
メンタルケアカウンセラー
メンタルケアカウンセラーは、先程ご紹介した「メンタルケア心理士」の下位資格です。資格の認定を行っているのは、メンタルケア心理士と同じく、メンタルケア学術学会と一般財団法人・生涯学習開発財団、そして一般財団法人ヘルスケア産業推進財団の3団体。今回説明している3つのメンタルケア資格のなかでも非常に特徴的な点として、そもそも試験がありません。
メンタルケア学術学会が指定する認定校で、3ヶ月ほどかけて「メンタルケアカウンセラー講座」の受講を修了すれば、誰でも資格を取得できます。
メンタルケアカウンセラーを活かせる仕事
試験を受けることなく、講座を受講するだけでメンタルケアについて学べるメンタルケアカウンセラーは、直接仕事に活かせる資格とはいいづらいです。あくまでも、メンタルケアの知識をこれから学んでいきたい人向けの資格となっています。
単独の資格で仕事に活かすのではなく、メンタルケアカウンセラー取得後にこころ検定やメンタルケア心理士、ケアストレスカウンセラーといったその他の資格に合格するための準備として利用するとよいでしょう。
メンタルケアカウンセラー講座の受講資格
メンタルケアカウンセラー講座は、受講料を払えば誰でも受講可能です。
メンタルケアカウンセラーの講座内容
講座では、メンタルヘルス・心理学・カウンセリングの基本について学んでいきます。
その他の資格と違う点
メンタルヘルスケアに興味を持つ、初心者向けの手頃な資格です。まずは講座でメンタルヘルスケアカウンセラーを取得し、それから別の資格へとステップアップしていきましょう。また、自分のペースで学習を進められる通信講座なので、なかなかスクールに通う時間が取れない人にもおすすめです。
メンタルケアを学べるスクール
| ヒューマンアカデミー |
|
|---|---|
| 特徴 |
通学制・通信講座のどちらでもメンタルヘルスを学習することが可能。心理カウンセリング・メンタルヘルスに役立つ「NLPプラクティショナー」や、メンタルケア学術学会が認定する「メンタルケアカウンセラー」資格(公的学会認定資格)などを取得できます。 |
| リカレント メンタルヘルススクール |
|
|---|---|
| 特徴 | メンタルヘルス対策のプロフェッショナルを養成するEAP専門スクール。EAP(Employee Assistance Program)とは従業員支援プログラムのことであり、主にビジネス関連のメンタルヘルスを学ぶことができます。 大学の心理学科・大学院の専攻レベルの内容を初心者でも習得できるよう、段階的なカリキュラムを組んでいるのが特徴。修了後は、年に2回行われる試験をパスすることで「EAPメンタルヘルスカウンセラー」「メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種・Ⅱ種」を取得可能。 |