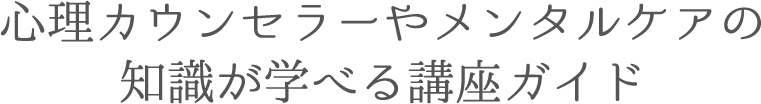「心理カウンセラーになりたい」、「メンタルケアを学びたい」あなたを応援するサイト
スクールカウンセラーの仕事について
小中学校や高校などの教育機関で、生徒の不登校や問題行動、いじめなどに対応するのがスクールカウンセラーの仕事です。文部科学省がスクールカウンセラー事業を積極的に推進していることにより、ニーズが高まっているスクールカウンセラーの業務内容について紹介します。
スクールカウンセラーとは
スクールカウンセラーとは、年々増えている不登校や校内暴力などへの対処法として、文科省が全国の小中高校へ積極的に配置している心理学の専門相談員です。現在、日本には1万5,000校以上の学校にスクールカウンセラーが配置されており、重要度がどんどん高まってきています。
スクールカウンセラーの仕事は、生徒の相談にあたるだけでなく、教職員や保護者に対する助言や援助、各専門機関と調整して連携を取っていくことなども求められます。そのため、スクールカウンセラーには、心理カウンセラーとしての相談能力に加えて、保護者や関係機関と連携を取っていく実務的な能力も求められます。
スクールカウンセラーの仕事の内容は?
生徒に対する相談では、不登校に関する内容が最も多いです。内容は、いじめ問題、交友関係、学習関係の問題など多岐にわたります。こういった問題は、親にも関連があることが多いため、親に対する相談・援助も必要になってくるわけです。
また、最近では教職員がストレスを抱えることも多く、教職員のメンタルヘルスに関する役割も重要となっています。スクールカウンセラーが、学内の会議等に出席を求められることもあります。
スクールカウンセラーは、生徒や教職員などの評価をする仕事ではありません。そのため、学校という枠組みを外れて相談をすることができる「外部性」が必要になります。学校においてカウンセラーは「スクールカウンセラーなら心を許して相談できる」という雰囲気を醸し出し、心理学の専門家としての成果を上げています。
そのほか、学校で大きな事件が起こった時や災害の際などに、スクールカウンセラーがクローズアップされることもあります。このような緊急時の生徒の心の傷は非常に大きいものです。急性ストレス障害などを発症することも多く、生徒に対する心のケアが、スクールカウンセラーの役割として求められます。
いまやスクールカウンセラーは、学校になくてはならない存在と言ってもいいでしょう。
スクールカウンセラーになるには
スクールカウンセラーになるには、文部科学省の規定で臨床心理士、精神科医、大学教員の資格が必要です。臨床心理士の資格においては、スクールカウンセラーの9割以上が保有しています。
その他に、精神科以外の医師や臨床心理士の資格取得見込み者などが、準スクールカウンセラーとして、学校での相談業務にあたる場合もあります。
スクールカウンセラーの難易度は?
「スクールカウンセラー」という資格自体は存在しておらず、この仕事に従事するための必要資格としては臨床心理士や精神科医、大学教員が挙げられます。
スクールカウンセラーの仕事に就く人のほとんどが選んでいる資格が臨床心理士で、こちらの合格率は毎年ほぼ60%台。平成29年度の合格率は65.5%でした。
合格率だけを見ると難易度は低めに思えますが、臨床心理士の受験資格を得るためには臨床心理士養成に関する指定大学院または専門職大学院などの修了が必要なので「受験自体が狭き門」とも言えます。その点まで考えると、決して難易度の低い資格とは言えません。
そして精神科医となるとさらに難関です。医師免許だけでなく、精神保健指定医という資格も取得しなければなりません。
精神保健指定医の資格申請には、精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験がある精神科医が講習を受けた上で所定のケースレポートを8例提出することが必要で、スクールカウンセラーになるためのルートの中でも、超難関ルートとなってしまいます。
実際にスクールカウンセラーとして活躍する人の体験談
- 私は大学卒業後しばらく一般企業でサラリーマンをしていましたが、どうしてもカウンセラーになる夢が諦められず、大学院に通って臨床心理士の資格を取りました。今はスクールカウンセラーと専門学校の非常勤講師の仕事を掛け持ちしています。
カウンセラーの仕事は待遇が良いとは言えず、給料の面でも厳しいこともありますが、やはり相談にきた生徒の笑顔を見ると、スクールカウンセラーになってよかったと感じます。カウンセラーは本当にやりがいのある仕事です。 - 非常勤のスクールカウンセラーをしながら、大学院での研究など、複数の仕事を兼務しながら働いています。
近頃はカウンセラーに対する見方も少しずつ変化してきましたし、ニーズも高まってきました。が、やはり職場によっては誤解を受けることもあるので、心理学の知識だけでなく、コミュニケーション能力や営業スキルなどもカウンセラーには必要かもしれません。
つらいこともありますが、カウンセリングに来た人が問題に向き合い、明るく健康な姿を取り戻していくのを見ると、何ともいえない達成感と喜びを感じます。 - スクールカウンセラーの資格を習得するのに必ず学校に通わないといけないということはありません。完全の独学は難しいかもしれませんが、通信講座を利用して資格を保有した方もたくさんいます。
実務に関して重要になるのは、やはり校長先生や教頭先生。学校側の方針に従って業務にあたることも少なくありません。また、クラス内での問題が多いため、担任の先生や生徒指導主任とも密に情報を共有しておくとよいでしょう。 - 生徒から話を聞くだけがスクールカウンセラーの仕事ではありません。校内の問題を探る上で、展示物・掲示物にいたずらはされていないか、きちんと貼られているかといったことや、保健室の出入りはどのようになっているかなども視野にいれておく必要があります。
また、カウンセラーはあくまでも先生ではない、身近な第三者の大人ということ。どんな話でも話してもらえるように、穏やかに話を聞いてみましょう。特にいじめが問題とされたときには被害にあっている生徒だけでなく、加害者側のカウンセリングも必要です。最近では、一ついじめの問題が片付くと、いじめていた子がいじめられるようになるケースもあります。カウンセラーという立場を活かして、両者をサポートできるとよいですね。